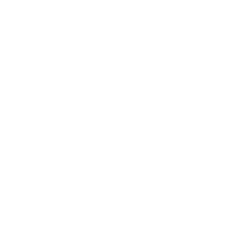目次
駆動概論
駆動系はエンジンが生み出した動力をタイヤに伝える機構の総称である。地味ではあるが、駆動系がきちんと機能しないとせっかくエンジンやシャシーが万全の状態でも車は走ることすらできない。精度と信頼性が要求される非常に重要な分野といえる。
また,駆動ユニットの構成部品であるLSD(ディファレンシャル)は車両の挙動にかなり大きな影響を与える.
構造解析,振動(共振)解析,液体(潤滑油/グリース)密閉,高精度な機械加工,車両運動…等々,駆動は突き詰めると奥が深いのである.
構成パーツ
ここでは主にUTFF18/UTFF19のパーツについて説明する。
出力軸サポート(通称軸サポ)
軸サポの詳細な説明に入る前に、なぜ軸サポという部品が必要なのかというところから説明する。一般的なバイクはチェーンドライブを採用し、チェーンでエンジン回転を後輪に伝えているが、UTFFで現在使用しているスカイウェイブ650はエンジンの回転を5つの歯車から構成されるファイナルギアユニットによって後輪に伝えている。このファイナルギアユニットはエンジンとは独立した機構となっており、エンジンからのびる長いシャフト(エンジン出力軸)が一番前方の歯車に挿入される仕組みになっている。UTFFではこのファイナルギアユニットを取り外して、歯車の代わりにドライブスプロケットを出力軸に嵌合させ、無理やりチェーンドライブにして使用している。このチェーンドライブ化に伴い二つの問題が生じる。一つはドライブスプロケットの軸方向の固定である。通常のバイク用のエンジンの出力軸にはドライブスプロケットを固定するためのプレートが嵌る溝が彫ってあるが、スカイウェイブ650のエンジンにはない。もう一つ、出力軸の折損である。スカイウェイブ650 のエンジン出力軸は片持ちで使用されることを想定していない設計になっており、そのままチェーンドライブにしてしまうとチェーンテンションによって出力軸が折損してしまう。この二つの問題を解決するために考え出されたのが、出力軸サポートという部品である。エンジン出力軸とデフキャリアの間に突っ張りを設けることで、チェーンテンションが出力軸にかかるのを防ぎ、同時にドライブスプロケットの固定問題を一応解決してくれるのである(軸方向の固定は軸サポの剛性に頼っているので、機械的な固定とはいえない)。このように軸サポはスカイウェイブ650のエンジンを使用するからこそ必要なUTFF独自の部品なのである。
UTFF17では工数削減がコンセプトであったため、フレームの簡略化のためリアバルクヘッドは設けず、フレーム後端のMHBSは一本のパイプのみで構成されていた。そのためデフユニットはフレーム後端のMHBSから吊り下がる形で搭載され、その下端に接続された軸サポはチェーンテンションと平行になっていなかった。デフキャリアのステーがフレームのノードについていなかったこともあり、17で実施したダイナパックテストでは駆動系とフレームが負荷に耐えられず、出力軸やMHBS、軸サポなどが降伏してしまった。そこで18では駆動系の信頼性確保を何よりの優先課題とし、軸サポを可能な限りチェーンテンションと平行にすること、デフキャリアのステーをフレームのノードにつけること、軸サポの強度を上げることなどに取り組んだ。
ドライブスプロケット
上の説明にもあるようにスカイウェイブ650の出力軸は特殊なので、一般的なバイク用のドライブスプロケットをそのまま使用することはできない。また軸サポのベアリングと嵌合する必要もあるので、ボスがついた形状でなければならない。このような事情から、ドライブスプロケットは駒場Ⅱキャンパスの生産技術研究所試作工場に特注していた。ところが17で製作してもらったスプロケットは内側のスプラインの軸と外側のボスの軸が合っておらず芯振れが生じてしまった(公差指定をしなかった我々がいけないのだが、試作工場の製作精度は過信してはならない)。試作工場側からもドライブスプロケットを一から作るのは大変なので、ミスミで買えるような市販の産業用スプロケットを追加工するだけで済むような設計にしてほしいというような要望もいただいた。そこで18では設計を変更し、チェーンサイズを往来使っていた520から50(530)にサイズアップした。このチェーンサイズの規格はバイク用のものであるが、50(530)というサイズだけは産業用スプロケットにも設定があるため、50(530)に変更すればミスミの市販品を使用できるようになるというわけである(サイズアップしたことで重くなった代わりに耐久性も向上した)。18ではSP50B15-S-12というスプロケットをミスミで購入し、試作工場にボスの外周の切削とスプライン加工をお願いした。市販品なのですでに焼き入れがしてあるため、結果的にコスト削減につながったほか、精度も17と比べて格段に良くなった。なお、ボスの外周を削るのは嵌合する自動調心軸受の内径に合わせるためである。またスプライン加工をお願いする際は振れ公差を指定し、エンジン出力軸のお貸しして現物合わせで加工を行っていただくことになる。その間はエンジンパートから出力軸を借りる必要があるので、事前に調整が必要である。
18で生じたドライブスプロケット周りのトラブルとしては、5月のシェイクダウンの際にドライブスプロケットが軸受から外れるという事故があった。市販品を使用したためボスの軸方向の長さを確保できず、圧入してもすぐに外れてしまうのが原因であった。そこで軸受を挟んだドライブスプロケットの反対側に抜け防止用のアルミパーツを装着し、スプロケットとそのアルミパーツをM4ボルト3つで締結した。その結果ドライブスプロケットの抜けはなくなり、その後の走行では問題は生じなかった。
自動調心軸受
上の説明にあるように、17のドライブスプロケットは内側のスプラインの軸と外側のボスの軸が合っておらず芯振れが生じてしまった。もともとは深溝玉軸受を使用する予定であったが、この問題に対応するため自動調心ころ軸受に変更した。ただ、軸サポはエンジンとシャシーをつないでいる部品なので、芯振れがなかったとしても、シャシーフレックスを吸収する意味合いで自動調心軸受を使用するべきである。なお、自動調心軸受にはころ軸受と玉軸受があるが、ここではより大きなラジアル荷重に耐えられるころ軸受を採用している。18で使用したベアリングは22207EAW33である。組付けの前のグリスアップは忘れずに行うこと。軸受は軸サポのベアリングハウジングに圧入して使用する。
ベアリングハウジング
ベアリングを圧入する先の筒状の部品をベアリングハウジングと呼んでいる。17・18では軸サポ本体に鋼管を使用していたため、鋼鉄(S45C)の中実棒から旋盤で削り出して作っていた。形状自体は非常にシンプルで作りやすいが、サイズが大きく、また内径の精度が極めて高い水準で要求されるため、製作にはかなり時間がかかる(昨年は製作に丸一日を要した)。大まかな作り方は、中実棒にドリルで徐々に大きな穴をあけていき、ある程度大きな穴があいたら中ぐりバイトとマイクロゲージを使いながら徐々に目標の寸法まで削っていく。削りすぎるとやり直しがきかないので、また一から作り直す必要がある。なお中実棒から削り出すと残留応力の関係で歪が出やすいので、来年以降も鋼鉄製にする場合は、鋼管(肉厚20mm程度のSTKM13A)を購入してそこから削り出すほうが楽なうえに精度が出やすいと思われる。
出力軸サポート本体
軸サポ本体の設計で注意しなければならないのは、トライブスプロケットとドリブンスプロケットがきちんとアラインされてないといけない点である。CAD上で慎重に寸法を決めていってほしい。軸サポの本体は鋼管(STKMR11A)を組み合わせて溶接して製作していた。17では25×25t1.2を使用していたが、ダイナパックでの事故を踏まえ信頼性確保を優先し18ではt1.6とした。
パイプのすり合わせはコンターマシンで行えば問題ない。デフキャリアと接続するパイプは溶接前にフライス盤での溝入れ加工が必要なので注意が必要である。溶接する際はパイプとベアリングハウジングを治具で固定して行っていた。ただし寸法通りに治具を製作してもどうしても歪みが生じてしまうので、最終的にはバーナーなどであぶってパイプを曲げながら調整した。経験上左右のパイプは内側に1mmずれてしまうので、治具の間隔をあらかじめ1mm余分に取っておくと後々楽である。このように溶接で製作すると精度が出にくいので、軸サポ自体をアルミから削り出すアイデアもあったが、まだ具体的な案にはなっていない。
チェーンテンショナー
軸サポには出力軸の折損防止とスプロケットの固定のほかに、チェーンテンションの調整も行える機構がついている。アルミ製のエンドバーツと呼ばれる部品を組み合わせ、デフキャリアが軸サポに接続する点を前後に移動させることによりドライブスプロケットとドリブンスプロケットの距離を調整し、最適のチェーンテンションを得ることができる。なお一般的な学生フォーミュラ車両では、ロッドやシムなどを用いてチェーンテンションを調整している。
18の大会のエンデュランス直前にチェーンテンションのゆるみが確認された。急遽ピットに戻って急いで調整したので大きな影響はなかったものの、ゆるみ防止のために19以降もさらなる対策が必要かと思われる。
エンドパーツ(内)
軸サポ本体のパイプの内側にすっぽりはまるアルミパーツである。フライス盤とボール盤を使えば簡単に製作できる部品である。長手方向にはM8のねじ穴が、短手方向には8mmのキリ穴があいている。長手方向のねじ穴にはチェーンのテンションを調整するための六角穴付きボルトが挿入される。18ではこのボルトの緩み防止のためにロックインサートを挿入していた(正しい使い方ではないのでポジティブロックとは言えないものの、ワイヤリングだけでは心細いのでとりあえず挿入した)。短手方向の穴には軸サポとデフキャリアを締結するためのボルトが挿入される。この二つの穴は十字に交差するため、チェーンテンション調整用のボルトが長すぎると短手方向のボルトと干渉して最悪破損してしまうので、ボルトの適切な長さを事前に見積もる必要がある。また、パーツの外寸を軸サポのパイプの内側の寸法ギリギリで製作すると内側で嵌って抜けなくなってしまうので、やすりで多めに面取りすることでスムーズに動くようになる。
エンドパーツ(外)
内側のエンドパーツに接続するチェーンテンション調整用ボルトの面圧を受けるための部品が外側のエンドパーツである。これもアルミ製の部品で、フライス盤とボール盤を使って簡単に製作できる。軸サポ本体の端部に蓋をするような形で使用する。真ん中にボルトが通るための8mmのキリ穴があいているほかにも、左右に小さい穴があいている。これはボルトのワイヤリングを通すための穴で、片方のワイヤーを軸サポの内側、片方のワイヤーを外側に通して、内側のワイヤーが軸サポの溝から出てきたところで合流させる。このエンドパーツは17ではコの字型の薄い形状をしていたが、ダイナパックの事故で破損したのをきっかけにかなり分厚い形状に変更した。
チェーン
18ではチェーンサイズ50(530)を使用した(変更の経緯についてはドライブスプロケットの節を参照のこと)。D.I.D(大同工業)のバイク用チェーン530VX-110ZBをアマゾンで購入して使用していた。メッキありとなしの品種があるので、耐久性の観点からメッキありのものを買うのがよい。ゴールドとシルバーは見た目の問題なので、好きな方を選べばよいだろう。チェーンを装着する際は、適切な長さになるようにチェーンをカットし(グラインダーで任意のピンの頭を削り落とせば長さを調節できる)、専用のカシメ工具を使用して接続する。カシメ工具は安いものを買うと一度の使用で壊れてしまうので、高くてもきちんとしたものを購入するべきである。なお、駆動系の組付けをする際は順序の問題で、デフキャリアをステーに接続する前にあらかじめチェーンをスプロケットにかけておく必要がある。
チェーンシールド
チェーンが飛散防止のため、レギュレーションではチェーンガードの装着が義務付けられている(詳しくはT.7.2.5を参照)。谷川工業(曲げ加工.com)というところに発注して製作してもらっていた。幅80mmt3.2のボンデ鋼板を指定したRに曲げてもらっていた。設計の段階ではフレームへの固定や他の部品との干渉に気を付けてほしい。18では前方1か所、後方2か所でフレームに固定していた。ステーは現物合わせで無理やり溶接していた。
ディファレンシャルユニット
デファレンシャルギアの説明は草加先生のゼミでやっているはずなので省略するが(自信がない人は各自ネットや書籍などで勉強すること)、学生フォーミュラ車両にデフが必要かというと必ずしもそうとは限らない。UTFF08やSHIBA-4のS015のようにデフを省略したカートのような車両も過去には存在する。またデフを採用するにしても、デフには様々な種類が存在する。現状の学生フォーミュラはFCC製のシュアトラックLSDを採用するチームが大半を占めるが、それは必然ではない。デフの有無や選定はマシンの運動性能に大きく影響するため、マシンコンセプトを策定する段階からこのあたりの点についてはよく議論するべきである。ここではFCC Tracを採用した18に基づいた説明をするが、これが絶対というわけではないことを留意してほしい。
LSD(リミテッドスリップディファレンシャル)
UTFFでは10以来FCC TracというシュアトラックLSDを採用してきた(詳しいマニュアルや図面はFCC提供のものがサーバーに上がっているのでそちらを参照してほしい)。採用理由は軽量だからというのもあるが、どちらかというと設計やメンテナンスが楽だからという消極的な理由である(11の設計審査会では草加先生がFCC Tracの選定理由が根拠に乏しいとして不快感を示している)。本来このデフはオイルで満たされたデフケースの中に浸す用途で設計されているが、多くのチームではこのデフを裸の状態で使用するため、その潤滑方法が問題となる。グリスで潤滑するチームも存在するらしいが、UTFFではオイルが出入りする穴を溶接で封じて、デフの中に直接オイルを入れることで潤滑を行っている(オイルはドライブシャフトを挿入する穴から直接入れていた)。こうした使い方を想定しているものではないので、当然何もしなければケースの割面からオイルがにじみ出てしまう。そこで18ではデフを組み上げる際に割面に液体ガスケットを塗布していた。またデフを組み上げる際はカムの形状の違いと並び順に注意して行ってほしい。17では一度間違えて組んだ結果デフを破損しかけた。
オイルシール/オイルシールハウジング
デフの中はオイルで満たされているため、そのオイルが外に漏れださないための工夫が必要となる。割面は液体ガスケットを塗布すればなんとかなるが、ドライブシャフトを挿入する部分のオイル漏れ対策にはオイルシールとOリングを使用する必要がある。オイルシールはドライブシャフトを伝ってくるオイルの漏れを防ぎ、Oリングはデフを伝ってくるオイルの漏れを防ぐ。そしてこれらを収めるのがオイルシールハウジングである。このオイルシールハウジングはデフとデフキャリアをつなぐ機能ももっている。オイルシールハウジングはアルミ製で、工房で自作したが、内寸外寸ともに極めて精度が要求される部品であるため、製作に時間と手間がかかる。作り方は基本的には軸サポのベアリングハウジングと一緒で、旋盤でマイクロゲージを使いながら徐々に目標の寸法まで削っていく。ただしベアリングハウジングとは異なり表面粗さにも気を使わないといけないため、自作はとても大変な部品といえる。17のオイルシールハウジングの設計ではOリングは三角溝で使用する設計をとっていたが、Oリングの使い方としてはイレギュラーな部類になるので、18の設計では円筒溝で使用する設計に変更した。ところが18ではオイルシールハウジングを新造する余裕がなく、17のものを流用し、Oリングの代わりに液体ガスケットを塗布するという突貫工事で間に合わせた。その結果大会の車検でオイル漏れが指摘されてしまったので、来年以降は要改善である。
ドリブンスプロケット
ドリブンスプロケットはFCC Tracに直接ボルト締結して使用する。歯数決定の際は狙った最高速になるようエクセル表を用いてファイナルギアレシオを計算していた。17ではクロスに振りすぎていたので18ではワイドにしたが、ギアレシオとしては適正であったと思われる。17・18のドリブンスプロケットはX.A.M. Japanという会社に特注していた。ホームページに特注スプロケットのフォーム(特注寸法記入書)があるので、必要事項を記入すればその通りに製作してくれる。なお、17のスプロケットは寸法ミスによりFCC Tracにはまらないということがあったので、発注の際はくれぐれもそういったミスがないようにしてほしい。
デファレンシャルキャリア
デフキャリアはデフを支持するための部品であり、軸サポとフレームに接続する。A7075の板材にベアリング用の穴をNCフライスで彫ったあと、ワイヤーカットで切り取って製作していた。基本的には技術職員の指導を仰ぐ形で製作することになる。
ドライブシャフト
ドライブシャフトはスポンサーであるNTNより支援を受けている。NTNの支援の案内は毎年12月ごろにFA宛に届く。企画書などを提出し、審査を経て1月に支援が正式に決定する。NTNは決まった時期に決まった報告(大会エントリー報告やシェイクダウン報告など)を求めてくるので、支援ガイドラインを熟読の上忘れないようにしなければならない。品種はスズキバギーKingQuad400FS用のものを使用していた。発注をする際は左右のシャフトの長さを指定できるので、CAD上で測定すればよい。17ではリアのハブの中心とデフの中心が大きくずれておりドライブシャフトの角度が15度程度ついてしまっていたので、ドライブシャフトがデフから抜けるなどの不具合があった。そこで18ではリアハブとデフの中心が合うように設計した(その分アクスルを後ろにオフセットした)。ドライブシャフトをデフに組付ける際は、ドライブシャフトのCリングがデフ側の溝にはまるまでプラスチックハンマーでたたけばよい。逆に抜く際はスライディングハンマーを使用する。スライディングハンマーが手元にない場合は、力に任せて思いっきり抜けば案外簡単に抜ける。ハブ側の固定は、キャッスルナットと割りピンを用いて行う。キャッスルナットはM18×1.5で細目なので、発注の際は並目と間違えないよう注意が必要である。
メンテナンス
駆動定期的にメンテナンスする必要がある.信頼性を損なわないよう忘れずに行うこと.
車重オーダーの荷重が加わるので,他パートと比較して部品の消耗は早い.こまめに行うように心がける.
以下に手順を示す
チェーン
まず第一に,チェーンは消耗品である.学Fカーの走行頻度は,通常のバイクに比べて少ないとはいえ,使い続けているとチェーンは伸びてしまう.一定期間使用したら交換すること.
特にダイナパックでは大きな負担がかかるようだ.ダイナパック後は注意して伸びをチェックすると良いと思う.
また,1~2月に1回程度の頻度で清掃/潤滑油の塗布を行うと良い.動きがスムーズになり高い伝達効率が保てるし,スプロケットの摩耗も少なくなる.
具体的な方法は次のサイトが分かりやすい:https://didmc.com/maintenace/
チェーングリースは水に弱いので,雨天走行後は必ず潤滑剤を塗布すること.
スプロケット
スプロケットも消耗品であるので,摩耗が激しくなってきたら新品と交換すること.特にアルミニウム製のスプロケットは消耗がかなり早い.古いものを使い続けると歯飛びを起こす可能性があり危険である.
もしスプロケットの片方のみが削れている場合は,チェーンのアライメントが合っていない可能性があるので確認する.
デフ
定期的に内部を分解し,部品に焼き付きが無いか確認する.
グリースを塗り,漏れが無いようにシールして組み直す.